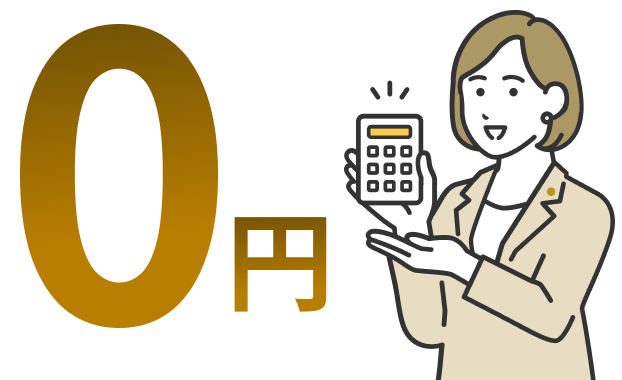除籍した子は相続人となるのか。離婚歴のある人の生前対策とは
- 遺産を残す方
- 除籍した子
- 相続
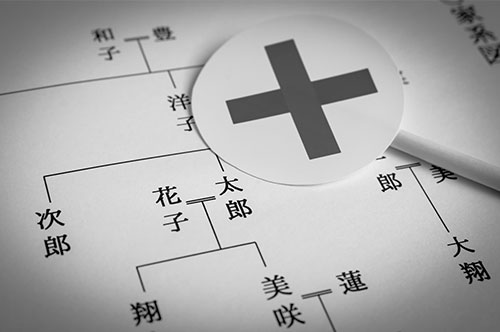
愛媛県内の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する紛争の件数は、最新の統計(令和2年)によると、年間約240件にものぼります。
相続で揉める原因としてよくみられるのは、主要な遺産が不動産で分割が難しいことや、面識がない相続人同士が遺産分割をすることが挙げられます。
財産を残す方に離婚歴があり、戸籍上除籍した子がいるといった事情がある場合、「相続人同士で揉めるのではないか」というご心配や、「疎遠になっている相続人には財産を残したくない」というご希望があるのではないでしょうか。
このようなケースでは、生前の相続対策がより一層重要です。今回のコラムでは、離婚などにより除籍した子がいる場合の相続に向けた準備について弁護士が解説します。
出典:「令和2年司法統計年報」(裁判所)


1、民法上、除籍された子でも公平に相続できる
民法では、相続人の範囲を次のように定めています。
- 第1順位:子と配偶者
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母)と配偶者
- 第3順位:兄弟姉妹と配偶者
被相続人(財産を残す方)が亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人となり、血縁関係のある親族のうち子が一人でもいれば配偶者とともに相続人となります。
ここでいう「子」とは、離婚した元配偶者との間の子や婚姻関係にない男女(内縁や愛人)間に生まれて認知された子も含まれます。
これらの子は、被相続人とは異なる戸籍に入籍しているケースが多いですが、親子関係や相続権が消滅することはありません。
これらの子の法定相続分は、出生時や出生後の経緯がどうであれ、等分とされています。
例えば、配偶者と子、さらに前の配偶者との間の子の3人が相続人である場合、相続分は配偶者が「2分の1」、子が「4分の1」ずつです。
なお、相続分というのは公平な相続の目安として民法で定められたもので、必ずしも相続分どおりに遺産を分け合う必要があるわけではありません。
2、相続手続きは、遺言の有無によって大きく異なる
相続手続きの流れは、遺言の有無によって大きく異なります。除籍された子の相続がどうなるかも同様です。それぞれのパターンについて大まかな流れを解説します。
-
(1)遺言がない場合
遺言がない場合の相続の手続きは大まかに次のような流れになります。
- ① 相続人と相続財産の確定
- ② 全相続人による遺産分割協議
- ③ 成立した遺産分割協議による名義変更
相続人と相続財産の確定もかなりたいへんな作業ですが、遺言がない場合に最も負担になることが多いのは、遺産分割協議です。
遺産分割協議について、民法では「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う」(民法906条)と規定するだけで具体的な分割方法は定められていません。
遺産分割協議は全相続人の合意がなければ成立しません。合意ができなければ、最終的には家庭裁判所の調停、審判により解決する必要があるため、1年以上かかるケースも珍しくありません。
身近な親族同士であっても揉めることが少なくなく、交流がない相続人が加わるとさらに難易度が上がることも覚悟したほうがよいでしょう。
なお、相続税の申告や納税は相続開始(被相続人が亡くなった時)から10か月以内に行う必要があるため、遺産分割が長期化すると納税資金の問題に直面することも考えられます。 -
(2)遺言がある場合
遺言は財産を遺す被相続人の最終的な意思表示として、相続手続きでは最大限尊重されます。
遺言をすれば誰に何を遺贈するのかを遺言者が自由に決めることができ、遺産分割協議は原則として行う必要がありません。
さらに、法定相続人以外の人や法人に財産を遺贈することも可能です。
遺言にはこのような強力な効力があることから、遺言書の作成には厳格な定めがあり、方式に違反すると、遺言が無効になることもあります。
さらに、誰に何を遺贈するのかという点でも、次の章で解説する遺留分には注意が必要です。
お問い合わせください。
3、遺言を作成する際は遺留分に注意
特定の相続人に手厚く財産を残したい、あるいは財産を残したくない、という希望がある場合は遺言の作成が不可欠です。しかし、遺留分という制度がよく問題になります。ここでは遺留分について解説していきます。
-
(1)一定の相続人に最低限の相続を保障する遺留分
相続には次世代に財産を引き継ぎ、遺族の生活を保障するという側面があるため、被相続人と関係が近い親族には、遺産から一定割合の取り分が保障されています。
これが「遺留分」という相続手続きの根幹をなす制度です。
遺留分が認められるのは、配偶者と第2順位までの血族相続人(子、直系尊属)で、遺留分の割合は相続人の構成により異なります。
例えば、被相続人が特定の人にすべての財産を遺贈するという遺言をしたとしても、遺留分がある配偶者や子は、受遺者に一定の金銭を請求できるわけです。
遺留分は遺留分権利者の権利なので、遺言によっても遺留分を制限することはできません。 -
(2)遺留分の計算方法
遺留分の金額は、遺留分の対象となる財産の額に遺留分の割合を掛け算して算定します。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。
配偶者Aと子B・Cが相続人である場合、法定相続分はAが「2分の1」、BとCが「4分の1ずつ」となるため、遺留分の割合は配偶者Aが「4分の1」、子B・Cが「8分の1ずつ」になります。
遺留分の対象となる財産の計算方法は、は少し複雑です。
被相続人の財産の総額から、借金などの債務の額を差し引いた額が基礎となる財産の額といえます。この金額に、生前になされた以下の贈与の額も加算されます。- 相続開始前1年以内にされた贈与
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与
- 相続開始前10年以内にされた相続人への贈与で特別受益にあたるもの
特別受益に当たる贈与とは、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」のことをいい、遺産の前渡しと評価されるような贈与が該当します。
生前の贈与が特別受益に当たるのかは、各人の経済状況などから法的に判断する必要があり、これが遺留分の計算を難しくしている一面があります。 -
(3)遺留分侵害額請求の時効
遺留分に満たない財産しか受け取ることができなかった相続人は、他の相続人に対して不足分を金銭で補償を請求(遺留分侵害額請求)することができます。
この遺留分侵害額請求権の時効にかかる期間は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年間です。
一方、疎遠になっている相続人は、自身が相続人になったことや、遺言により遺留分が侵害されていることを知らないこともありえます。
このようなケースでは、相続の開始から10年間遺留分侵害額請求権が存続します。 -
(4)事業承継のための贈与には特例がある
事業の後継者への株式や事業用資産に関する贈与については、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律により、遺留分算定の特例が認められています。
株式などの贈与について、全相続人の合意により遺留分算定から除外したり、評価額を合意の時点で固定したりすることができる制度です。
事業承継を円滑に行うためには、期間をかけて遺留分対策以外にもさまざまな準備を行うことをおすすめします。
4、遺産を渡したくない相続人がいる場合の生前対策
相続対策として遺言の作成は効果的ですが、遺産を渡したくない相続人がいる場合に行っておきたい対策について解説します。
-
(1)遺留分を放棄してもらう
財産を残す方が亡くなる前であっても、遺留分は放棄することができます。
遺産を渡したくない相続人に遺留分を放棄してもらえれば、遺言どおりに遺産を配分しても法的紛争になる心配がなくなります。
ただし、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要で、誰かに強要されたり騙されたりしていないか、十分な代償が得られているかといった点が審査されます。
つまり、少なくとも遺留分に相当する金銭を代償金として支払うことを条件に遺留分を放棄してもらうということです。
相続を円満に進めるという面では有効な方法ですが、遺留分相当額を前もって渡さなければならないのがネックになります。 -
(2)生前贈与をする
多くの財産を残したい人に、生前から贈与をして財産を移転しておくのも有効な方法です。ただし、贈与が特別受益に該当すると遺留分算定の財産額に加算されてしまう点がネックになります。
生前贈与が特別受益となる可能性があるのは、相続開始前10年間に行ったものに限られるので、長期のプランで生前贈与を行うのがより効果的です。 -
(3)生命保険を活用する
遺留分侵害額請求を受けた場合の原資として、保険金受取人を身近な親族とする生命保険契約を締結しておくことも有効な方法です。
生命保険金は保険金受取人の財産とみなされるため、遺産として扱う必要はありません。
ただし、あまりにも高額な生命保険契約を締結してしまうと、高額な保険料により財産を減少させて保険金受取人が多額の保険金を得るという不公平が生じてしまいます。
そのようなケースでは、保険金が特別受益とみなされて遺産に持ち戻される可能性もあるので注意が必要です。
希望どおりの遺言をした上で、遺留分侵害額請求をされた場合にも備えることができるため、より現実的な方法といえるでしょう。 -
(4)廃除する
廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行がある相続人に対して、家庭裁判所の手続きにより相続権を剥奪する制度です。
しかし、相続権の剥奪を安易に認めると遺留分制度を認めた相続法秩序を混乱させるおそれが大きいことから、よほどのことがなければ廃除は認めないというのが家庭裁判所のスタンスといえます。
単に性格が合わない、疎遠であるというような理由で認められるものではありません。
5、相続対策はベリーベスト法律事務所にご相談を
相続の問題は、法律に従って手続きを進める必要があるのはもちろんのこと、贈与税や相続税、不動産登記など幅広い専門分野に関する知見が必要です。
相続対策をしたいと考えられても、どの専門家に相談すればいいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、相続問題の経験が豊富な弁護士と、グループ傘下の税理士や司法書士が連携し、お客様をサポートすることも可能です。
また、お客様のニーズに応じて、相続だけではなく事業承継など各種専門チームと連携したサポートも可能です。
お問い合わせください。
6、まとめ
離婚歴がある過去の婚姻中に子をもうけた方の相続では、相続人の範囲が広くなり円満に相続が進まない可能性が高くなります。
このようなケースで遺産の配分に関するご希望がある場合には、早めに生前対策に取りかかるのが賢明です。
遺言書について、方式についても厳格な規定を守る必要があるほか、内容の合理性や遺留分への配慮も必要です。
また、遺言と合わせて生前贈与などの対策も、長期間計画的に行うとより効果的です。
今後、個人資産に対する課税強化の流れが強まることが予想されており、ご自身の資産を守る、引き継ぐことについて検討されてみてはいかがでしょうか。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|