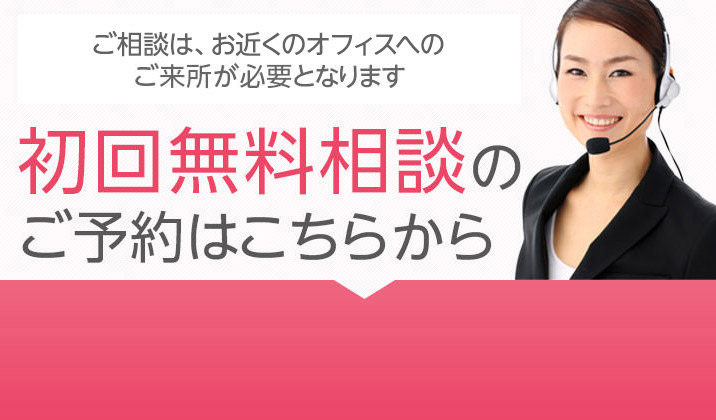妻が離婚後も夫名義の住宅ローンが残る自宅に住むとき留意すべきこと
- 離婚
- 離婚
- 住宅ローン

「松山市統計書(令和5年度版)」によると、令和5年に離婚が成立した件数は801件でした。
離婚を検討している夫婦のなかには、住宅ローンを組んで家を購入しているため、今後どうすべきか悩んでいるケースもあるでしょう。実際に、離婚後も子どもと一緒に家に住み続けられるのか、残った住宅ローンをどうするかといったご相談は少なくありません。
本コラムでは、離婚後に妻が子どもと一緒に家に住み続けたい場合に、住宅ローンの名義や支払いで気をつけたいポイントを、ベリーベスト法律事務所 松山オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚後に妻が住み続ける方法
まずは、妻(家の名義人ではない方)が住み続ける方法について解説します。
-
(1)元妻が住み続け、家の名義を元妻に変更し、住宅ローンを元妻の名義で借り換える
家や住宅ローンが元夫名義のままの場合、元夫が無断で家を売却したり、元夫が住宅ローンを滞納して何か月分もの支払いを請求されたりするリスクがあります。
このようなリスクをさけるには、元夫と家とのかかわりをなくすことが有効です。
そこで、家の名義を元妻に移転し、住宅ローンを元妻の名義で借り換えることが考えられます。こうすれば、元夫が無断で家を処分することはできませんし、ある日突然、多額の住宅ローンの支払いを請求されることもありません。
ただし、この方法には、次のようなデメリットもあります。
まず、住宅ローンの名義を変更するには金融機関の審査を通らなければならず、安定した収入が必要になります。そのため、この方法を利用できるのは、共働きで元妻にも相応の安定した収入がある場合に限られます。
また、いったん住宅ローンの借り換えをすれば、将来収入が減少しても住宅ローンの支払いを続けなければなりません。 -
(2)元妻が住み続けるが、家と住宅ローンは元夫名義のまま、支払いも元夫が続ける
元妻が住み続ける場合でもっとも多いのがこのパターンです。
生活環境を変えずにすむというメリットがあるだけでなく、場合によっては慰謝料や養育費代わりに無償で住むことができることもあります。
ただし、この方法を検討している場合、事前に金融機関と相談しておく必要があります。
住宅ローンは、契約者が住むことを条件としているものが多く、契約者である元夫が家を出て元妻と子どもだけが住み続ける場合、契約違反として金融機関からローンの残額を一括請求されるおそれがあるためです。
また、元夫が住宅ローンを滞納した場合、家を競売にかけられるおそれがあります。
離婚後に元夫の収入が減ったり、再婚して支出が増えたりといった可能性は十分にあります。そのような場合に元夫が、自分が住むならともかく、元妻が住んでいる家の住宅ローンを支払うために収入を増やす努力をすることは期待できません。
また、まだ住宅ローンが残っているような若い夫婦が、離婚する際に「元妻が死ぬまで無償で住んでよい」と約束することは現実的ではなく、いずれ元夫から家を出るように要求されるケースも少なくありません。
2、離婚後に妻が住み続ける以外の選択肢
妻が住み続けるには収入の条件やリスクもあるため、引っ越しを検討することもあるでしょう。その際の選択肢について解説します
-
(1)家と住宅ローンの名義は元夫のままで、元夫が住み続ける
このパターンも珍しくありません。元妻は家と関係なくなるため、突然住んでいる家を売られたり、住宅ローンの支払いを請求されたりといったリスクを負わずにすむというメリットがあります。
ただし、元妻は家を出て別の住居を確保する必要があり、子どもがいる場合には子どもへの影響も大きくなります。
また、家の現在の価値よりローンの残額が多い場合(いわゆるオーバーローンの場合)、財産分与は現存する財産を分けるものですから、元妻は原則として家に関して財産分与として何かをもらうことはできません。 -
(2)家を売却するという選択肢も
これまでは夫婦の一方が離婚後も住宅ローンを支払っていくことを前提とする選択肢を紹介しましたが、家を売却するという選択肢もあります。
家を売却する場合は、さらに次の2つに分けることができます。
① アンダーローンの場合
家の価値がローンの残額を上回る場合、家を売却し、ローンの残額を支払った後に余ったお金を、財産分与として分けることが一般的です。
② オーバーローンの場合
家の価値がローンの残額を下回る場合でも、債権者の同意を得て家を売却することができます。売却代金をローンの返済にあて、残った債務はもとの名義人が負担し続けることになります。
なお、親族などに購入してもらい、新たに所有者になった親族から家を賃借することができれば、もとの家に住み続けることもできます。
お問い合わせください。
3、妻が住み続ける場合のメリット
妻が住み続けることには次のようなメリットが考えられます。
-
(1)生活環境を変えずにすむ
最大のメリットは、離婚後も生活環境を変えずにすむということでしょう。
特に未成年の子どもがいる場合、離婚後にそれまでの家に住めないとなると、転校などが必要になります。親の離婚自体が子どもを大きく傷つけるうえに、転校などで友人とも別れることになれば、子どもの受ける精神的ショックは計り知れません。
少しでも子どもの精神的ショックをやわらげるためには、もとの生活環境をできる限り維持することが望ましいといえます。 -
(2)経済的な負担が軽減される
離婚して元妻が家を出る場合、新たに家を借りたり、家財道具をそろえたりするのにまとまったお金が必要になります。
これに対し、離婚後も元の家に住み続ける場合、家財道具をそろえる必要はありませんし、養育費や慰謝料の代わりに元夫に住宅ローンを支払ってもらえれば、家賃を負担する必要もありません。
特に専業主婦だった方には、経済的なメリットは大きいでしょう。
4、妻が住み続ける場合のリスク
元妻にとって、家に住み続けるメリットは大きい一方で、住宅ローンの名義などによって、次のようなリスクもあります。
-
(1)元夫が家を売却するおそれがある
家や住宅ローンは元夫名義で、元妻と子どもは家に住んでいるだけという場合、元夫は、元妻や子どもの承諾なしに家を処分することができます。
そのため、元夫が元妻や子どもが知らないうちに家を売却するおそれがあります。 -
(2)住宅ローンの支払いを請求されるおそれがある
共働きの夫婦の場合、夫の名義で住宅ローンを組み、妻が連帯保証人になることがあります。この場合、元夫が住宅ローンの支払いを滞納すると、元妻に住宅ローンを支払うよう請求されます。
5、離婚時の住宅ローン手続きで気をつけておきたいポイント
最後に、元妻が離婚後も家に住み続ける場合の手続きにおいて、気をつけておきたいポイントを紹介します。
-
(1)公正証書を作成する
公正証書とは、公証人という公務員が作成する公文書のことです。
離婚について話し合いをして合意ができた場合、口約束だけでは後から「言った・言わない」の争いになるおそれがあります。また、自分たちで作った文書は一応の証拠にはなりますが、それだけで合意内容を強制執行することはできず、裁判などを起こす必要があります。
これに対して、公正証書は証拠としての価値が高いうえに、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておけば裁判を経ることなく差し押さえなどの強制執行をすることが可能になります。
元妻が家に住み続け、元夫が住宅ローンを支払う場合、元夫自身が住んでいない家のローンの支払いをしてくれる保証がないというのが最大の問題です。
このリスクを少しでも軽減するために、公正証書を作成しておくことが必要になるのです。
ここで重要なことは、公正証書に「元夫が住宅ローンを支払う」と書くだけでは元夫が支払いをしないときでも強制執行ができないことです。
強制執行ができるようにするには、元夫が住宅ローンを直接金融機関に支払うのではなく、「元夫が住宅ローンの返済に相当するお金を元妻に支払い」、「元妻が金融機関に支払う」という2つの約束をすることが考えられます。 -
(2)家の名義変更
元妻が住み続けるだけでなく、元妻が家の所有権を取得する場合には、家の名義変更に関して気をつけなければならないことがあります。
この場合、元夫名義のままだと元夫が無断で処分することができるため、元妻は当然、名義を変更してほしいと考えるでしょう。
不動産の所有権と住宅ローンは直接の関係はなく、不動産の名義を変更しても担保権は消えないので、住宅ローンが残っていても元妻に名義変更することは理論的には可能です。
ただし、住宅ローンには、名義変更に金融機関の承諾を必要とするという内容の条項が含まれていることが多く、金融機関はなかなか承諾してくれません。
もし金融機関に無断で名義変更すると、契約違反だとして一括請求されるおそれがあり、支払いができない場合には、担保権を実行されて家を競売にかけられてしまいます。
そのため、名義変更をする前に、必ず金融機関に相談するようにしましょう。
金融機関が承諾してくれない場合には、住宅ローン完済後に元妻に名義を変更することを合意し、公正証書に残しておくといいでしょう。 -
(3)元妻が連帯保証人から抜けることは難しい
元夫名義で住宅ローンを組み、元妻が連帯保証人になっているというケースがあります。このようなケースで離婚後に元夫が住み続ける場合、元妻は、家のことはもう自分には関係がないから連帯保証人から抜けたいと思うでしょう。
しかし、連帯保証契約は、連帯保証人と金融機関の間で結ばれる契約です。そのため、離婚時に元夫に「保証人から外して」と言っても、元夫の意思だけで外せるものではなく、金融機関の承諾が必要になるのです。
金融機関は、主債務者(住宅ローンの名義人)が支払えなくなったときに備えて連帯保証人を立てさせているため、簡単には連帯保証人から抜けさせてくれません。
不動産などの資産か安定した収入のある別の人が連帯保証人になってくれれば抜けられる可能性はありますが、離婚の協議に入るほど関係が悪化している段階で夫に対し、「自分は保証人を抜けたいので、あなたの方で代わりの保証人を探して」と頼んでも、夫がどれだけ真剣に代わりの保証人を探すかは疑問です。
よって、連帯保証人から抜けることはかなり難しいと言わざるを得ません。
お問い合わせください。
6、まとめ
妻が家に住み続けることには経済面などでメリットが大きいものの、もとの住宅ローンの名義や離婚後に名義を変更するかなど、それぞれの事情によってメリット・デメリットが異なります。それぞれの事情にあわせた最適の方法を選択するには、専門的な知識が不可欠です。
ベリーベスト法律事務所 松山オフィスには、離婚問題の取り扱い実績が豊富な弁護士が所属しています。離婚問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています